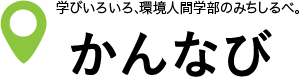【& Dialogue】管理栄養士の仕事は、人と関わり、幸せを願うこと。

環境人間学部には、環境との関わりの中で育まれる「人間の食生活」の解明と創造を目的とした食環境栄養課程があります。当課程では、食と栄養・健康について専門的に学びながら管理栄養士の資格取得をめざします。食と健康のプロフェッショナルである管理栄養士の資格を取得した学生には、どんな可能性が待っているのでしょうか?進路や就職について、教員3名が熱く語り合いました。
右)坂本 薫:食環境栄養課程 教授/調理科学、食生活科学
中)伊藤美紀子:食環境栄養課程 教授/臨床栄養、病態栄養、代謝栄養
左)永井成美:食環境栄養課程 教授/栄養生理学、時間栄養学、栄養教育 (司会)
管理栄養士のおもしろさ、やりがいを知ってほしい
永井:2024年9月から2025年3月まで放映されていたNHKの朝ドラ「おむすび」は、管理栄養士が主役。このドラマで管理栄養士という職業を知った!という方もいらっしゃるかと思います。今回は、管理栄養士に興味がある高校生や保護者の方々に、管理栄養士という仕事や、そのおもしろさ、やりがいを知っていただこうという企画です。
今日は、食環境栄養課程の坂本先生と伊藤先生にお話をうかがいます。自己紹介から、よろしくお願いいたします。
坂本:よろしくお願いします。給食関係の科目を担当しています。給食というのは大量調理で、家庭での調理と違って徹底した衛生管理を行う必要がありますが、作業を管理しながら、おいしくて栄養バランスの整った食事をどのように提供するか、について学ぶ科目です。実習も多くあります。私は、食品が食べ物になる過程でどのような変化が起こり、栄養的にどんな効果があるのか、おいしさにどのような違いが出るのか、等について研究しており、学校給食が児童生徒にどんな影響を及ぼすのか、という調査も行っています。
伊藤:臨床栄養を担当しています。朝ドラ「おむすび」に出てくるような病院や高齢者施設、障がい者施設などの特別な配慮が必要な方に向けた栄養・食事療法に関する講義、実習を担当しています。専門は、食事制限が多い腎臓の悪い方の食事をよりよくできないか?というような研究。食べたら体の中でどうなるのか、食べるものを少し変えることで予防や改善につなげるにはどうすればいいのかを考え、基礎的な研究や患者さんの調査を行っています。
永井:ありがとうございます。本日進行役を務めます私は、患者さんや一般の方に、専門的な知識を易しく、かつ正確に伝えるための栄養教育の授業や実習を担当しています。また、いつどのように食べると体に良いのか?という時間栄養学の研究も進めています。
管理栄養士の仕事は、病院や社員食堂の管理栄養士、スポーツ栄養士、お弁当の会社でのメニュー開発など色々あることが、朝ドラ「おむすび」の中でもちらっと見えました。今日は、管理栄養士という仕事や学生の進路について、さらに、そのおもしろさとやりがいについてお話しいただけたらと思います。

給食を、食事で終わらせないで教材に
坂本:満足に食事を摂れない子どもたちを救うために始まった学校給食ですが、その後、十分に食べられるようになってきて、給食はもう必要ないのでは?という議論が行われた時代もありました。しかし、再び給食の意義が見直され、社員食堂での給食が大人気になって話題になるなどしています。好きなときに、手軽に、いろんな食べものが買える今、子どもたちの食生活や食の育ちにおいて、給食を食べるということが非常に重要になってきています。このことは大人にとっても同様です。
永井:食の育ち、つまり食育という意味で、給食は、まさに生きた教材ですね。日々の給食を題材に、「今日は地元の野菜を給食に出していますよ」とか、「牛乳を飲むのは、こういう理由ですよ」とか、給食を教材にして、子どもたちに日々食教育をしていくことも学校給食の重要な側面ですね。
坂本:例えば、パスタとおにぎりを食べたり、サンドイッチとうどんを食べたり、自由に好きなものを食べればいい!というような食生活を続けていては健康は守れませんし、伝統的な和食の献立構成の良さも継承されません。正しい知識をもって食事をすることが健康を守ることにつながるので、給食で食のあり方を学ぶことは、生涯の財産になります。

坂本 薫 教授
病院では直接患者さんと 食に関するお話をし、多職種で連携する
伊藤:以前は、管理栄養士といえば病院の給食を作っているイメージが強かったと思うんです。昔、病院の管理栄養士は病院食というモノが対象だと言われていましたが、今は患者さんと直接お話をする、人を対象とした仕事になっています。実際に給食を作るだけでなく、患者さんのベッドまで行って話を聞いたり、1人1人に合う食事や栄養療法を提案したり、と患者さんの栄養管理をしていくのが仕事であり、ここ20年で大きく変わったポイントのひとつです。退院後食事療法を実践していただくのは患者さんご自身なので、病院の管理栄養士は、患者さんのサポーターなのだと私は思っています。
永井:朝ドラ「おむすび」の中では、患者さんのお食事の様子をベッドサイドに行き観察するミールラウンドという言葉や、医師や看護師らと連携するNST(Nutrition Support Team)という言葉が頻繁に出てきました。
伊藤:NSTは、栄養サポートチームのことです。医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師などが集まって、例えば低栄養状態の患者さんや栄養上の問題がある方やこれまで食べられなかった方に少しでも食べていただくにはどうすれば良いのか、非常に痩せておられる方の体調をどうやって戻そうかということを多職種で話し合い、患者さんの病態の改善につなげています。NSTはアメリカで広まり、日本に入ってきて、今では多くの病院で導入されています。実際、管理栄養士が主体となってNSTを進めている病院もたくさんあります。

伊藤 美紀子 教授
管理栄養士は、活躍できる舞台が数多い
永井:管理栄養士が活躍している職場って、他にどんなところがあるんでしょうか?
伊藤:活躍可能な場がたくさんあって、幅広いのが特徴ですよね。
坂本:そう思います。管理栄養士の大事な仕事のひとつが、人と接すること。「給食が教材だ」という話につながることとして、退院後もご家庭でなるべくいい状態の食事をしていただくために、お手本になる食事を実際に食べていただく「教育入院」を行うこともあります。
また、食事を提供する施設では管理栄養士が必要になります。特別養護老人ホームなど入所施設での食事は日々の楽しみであり、健康を維持するためにも非常に重要です。入所者さんの健康状態を見ながら食事を提供し、要望を聞いて、より質の高い生活をしていただけるように管理栄養士が気を配ります。
永井:食事を提供する入所施設には、管理栄養士を必ず置かなければいけない施設もあり、就職先の1つとなっています。高齢者施設や保育園を複数有する、福祉法人に就職する人もいますね。
坂本:保育所以外にも、児童養護施設や乳児院などでも管理栄養士が活躍しています。保育園には、管理栄養士がいないといけないという決まりはないのですが、食育は子どもの頃から行うのが大切なので、園ごとに力を入れておられ、管理栄養士を採用している園もあります。食育がやりたいからと、子どものための施設に就職する卒業生もいますし、管理栄養士と栄養教諭の資格を活かして子ども連れで参加できる離乳食の料理教室を起業した卒業生もおり、子育てしながら活躍しています。自治体によっては、公立保育所に管理栄養士を配置しているところもあり、公務員として公立保育所で活躍している卒業生も何人かいますね。
ステップアップできる、 世界中に舞台がある
永井:企業のカフェテリアや社員食堂は、どうでしょう?
坂本:健康な人の食事作りにたずさわりたいと言って給食会社や社員食堂に就職する学生もいます。管理栄養士という職業の良さは、ステップアップできること。経験を踏まえて、どんどんステップアップしていけるのが魅力だと思います。例えば、施設や病院で食事を作る仕事をしていて、次は人と関わる仕事がしたいと思ったときに、食事を作っていた経験を活かしてステップアップすることもできますし、施設での給食づくりの経験を生かして、給食施設の指導を行う保健所の管理栄養士になった卒業生もいます。
永井:卒業して働いて、自分のやりたいこととちょっと違うなとか、こんなこともやってみたいなという時に、転職や大学院入学などの新たなチャレンジができ、道が1つじゃないっていうのも管理栄養士の特徴でしょうか。
伊藤:病院に就職してから、その経験を活かしてスポーツ栄養士をめざした学生もいますよね。
永井: JICA(国際協力機構)の隊員や職員として、国際栄養に携わる卒業生もいます。モンゴル国には日本が援助している日本式国立病院があるのですが、そこに、栄養の専門家として派遣されている卒業生がいます。学生時代に、卒業研究を首都のウランバートルで行ったことが、きっかけとなりました。他国の例では、フィリピンの保健所でJICA隊員として住民への栄養指導をした人、グァテマラで子どもの栄養不良対策に携わった人もいました。二人とも、今も、国際栄養の分野で活躍しています。

永井 成美 教授
狭き門ながら人気なのは、 スポーツ栄養士への道
永井:ところで、スポーツ栄養士(正式名称:公認スポーツ栄養士)は学生に人気ですね。メディアへの露出が多く花形の職業という印象なのでしょうか。でも、誰でもできる仕事ではなく、管理栄養士としての専門性に加えて、経験、人脈、コミュニケーション力、それにチャンスや運も必要です。仕事に就くまでのプロセスも、スポーツ栄養の研究ができる大学院に進学する、管理栄養士としての経験を積む傍らでスポーツ栄養の学会や勉強会で知識・人脈を広げるなど、さまざまです。スポーツ栄養に関わっている卒業生には、食品企業の研究所、給食委託会社、国の研究センター、大学に就職した人や、フリーランスのスポーツ栄養士として、プロスポーツチームやオリンピック選手などと契約して活動していた人がいます。
伊藤:私は、スポーツ栄養士になる方法の1つとして、病院への就職をおすすめしています。病院にはリハビリテーションという過程や、スポーツ外来がある病院もあります。そこで他職種と一緒にサポートすることもできますし、回復期のリハビリでは食事も考慮しながら筋肉をつけて体を整えることになり、その経験はスポーツ選手にも活かせるので、まず体を知る、経験を積むという意味でも病院はおすすめなのです。
永井:大手の給食委託会社がスポーツチームや選手のサポートをしている場合は、それらの会社への就職がチャンスになります。ただしスポーツ栄養に関わることのできる人は、会社の栄養士・管理栄養士の中でも、ほんのひと握りの人たちであることが多いのです。狭い門ですが、本学の卒業生にも、その「ひと握り」になった人はいます。
病院は、日々専門化・高度化が進んでいる
永井:管理栄養士は卒業して終わりではなく、日々勉強し、成長し続けていけるというお話がありました。
伊藤:変化が最も激しいのは、臨床栄養ですね。国の制度が2年に1回変わり、高血圧や糖尿病のガイドラインは、基本的に5年に1回変わります。色んなエビデンス(根拠、裏付け)や研究の結果をふまえ、これまではこうした方がいいと言われていた食事療法が違う方向に進むような場合もありますし、「なぜ?」「どうして?」「どうすれば?」という問いを頭に置きながら、常に新しい情報を収集し、学びながら患者さんと接していくことが必要だなと思います。
坂本:日々勉強ですよね。
伊藤:そうですね。毎年新しい教科書を使っていますが、ここは古いから、ここも古いから…と言いながら新しい情報を学んでいます。本当に日々変わり、どんどん発展していく分野だなと思います。まだまだ解明されていないことがあり、新しくわかることがいっぱいある。だから本当に常に勉強していく必要性がありますが、興味深い分野であると思っています。
永井:病院は特に臓器別とか疾患別とか、管理栄養士の専門化・高度化が進んでいるようですね。病棟への配置も増えていると聞きます。
伊藤:そう、病棟配置が増えています。多くの病院では、管理栄養士は病院全体の患者さんの栄養管理をしており、必要に応じて病棟に赴きます。看護の分野には、内科病棟の看護師、外科病棟の看護師というように、早くから病棟配置のシステムがあったのですが、人数が多くなかった管理栄養士には難しかったです。今は入院患者の栄養管理をさらに充実するためには病棟配置型の管理栄養士が望ましい姿として考えられるようになり、国にも評価されて、その体制を推進する病院も増えています。それに伴い、病院における就職の機会も増えています。
永井:まだ数としては少ないのですが、小児歯科医院や薬局などで、患者さんやお客さんに、食育や栄養相談を行う管理栄養士もいますね。

管理栄養士だからこその商品開発
永井:先ほどスポーツ栄養士が人気ということでしたが、「食品開発」ができる企業を志望する学生も多いですね。最終的には消費者という「ヒト」が対象の仕事ですが、管理栄養士の就職先として、いかがでしょうか?
坂本:卒業研究においても食品開発に直接役立つ研究に取り組む場合も多く、高齢の方が食べやすい、自力で飲み込みやすい食品の開発を行う企業に管理栄養士として就職している卒業生もいます。大学院に進んで、研究をさらに深めて専門性を高めてから希望の仕事に就く学生もいます。さまざまな食品がある中、管理栄養士だからこそできる商品開発があると思います。
伊藤:単においしいものとか珍しいものの開発は、他の学部の方でも可能です。けれど栄養的な配慮や、中身をちゃんと考えて体にいい食品を開発できるのは管理栄養士だからこそです。
坂本:管理栄養士の採用枠を設けている食品メーカーが増えています。栄養的な点と、飲み込みやすさや食感などを併せて開発できるのは、専門的な知識をそなえた管理栄養士ならではですよね。
伊藤:みなさんがご存知の大きなお菓子メーカーや食品メーカーが、高齢者が食べやすく飲み込みやすい咀嚼・嚥下(えんげ)食や、少量で高栄養なものをたくさん開発しています。コンビニに並んでいるような、大手のお菓子メーカーが作っていたりします。開発には、管理栄養士が関わっているはずです。
坂本:そのほか、離乳食なども、ですね。
永井:その会社の製品を使っての、メニュー開発も、でしょうか。
坂本:管理栄養士の活躍の場は、どんどん増えているなと思います。新たに管理栄養士枠を設けて採用したり、管理栄養士が商品開発を行う部署を新設したりしている企業もあると聞いています。
永井:商品開発以外にも、例えば醤油メーカーだったら、醤油を使った健康的なメニューをホームページに載せたり、醤油から派生する食べ物を開発したり、管理栄養士が「食べる」ことを調整していく、そういう仕事が出てきている印象があります。
坂本:環境人間学部ならではのSDGsに関わる研究開発もありますね。
食あるところに、管理栄養士の舞台あり
永井:管理栄養士養成校の中には、管理栄養士の資格取得がゴールとして設定され、卒業研究を行わないところもあります。しかし、卒後、さらに成長するためには、卒業研究が非常に有効であり、それをしっかりやっているところが本学の特徴です。3年生から少人数でゼミに配属され、4年生で研究力や探究力を磨くことが、卒業後の大きな成長につながっていると実感しています。この点はいかがですか?
坂本:話題にあがった企業の研究開発でも、大学や大学院での研究が活かせるフィールドで管理栄養士の知識が役立ち、活躍しているなと感じています。
伊藤:病院に目を向けても、卒業生が近隣の病院や実習先になっている病院で活躍しているため、自分の後輩だからと実習を受け入れてくれたりしますし、みんながんばっているんだとうれしく思っています。病院に入ると、糖尿病療養指導士やがん病態栄養専門管理栄養士、アレルギーや子どもの専門であるとか、プラスアルファの認定資格が取れるため、専門性をさらに高めていけます。実際、専門性を磨きながらキャリアアップを重ねている卒業生もたくさんいます。
永井:管理栄養士の資格を取得した人たちのキャリアの方向をまとめると、学校系(栄養教諭)、病院系、福祉施設系(高齢者介護施設、障がい者福祉施設、児童福祉施設(注)保育所など)、企業のカフェテリア、食品メーカー、行政系(保健所、保健センター)、フリーランス、スポーツ栄養など、でしょうか。「食あるところに、管理栄養士あり」という状況になってきているようです。
食や栄養の専門的な知識で、 人を幸せにする仕事
永井:最後に、管理栄養士というキャリアに興味を持っている高校生に、ひとことお願いします。
坂本:これまでに話題にあがっていない就職先として大学関係、研究職があります。修士課程だけでなく博士課程まで一貫して学ぶことが可能な兵庫県立大学は、非常に恵まれた環境にあると言えます。管理栄養士の資格を持って修士、博士が取得できます。大学院修了後、大学に勤めて、管理栄養士養成に携わりながら研究を続けている卒業生も増えてきています。これからさらに多くの卒業生が大学で教育・研究において活躍してくれるものと期待しています。
永井:企業系の研究職と大学の研究職の違いは、どういう点にあるのでしょう?
伊藤:企業の場合は商品開発、食品の開発になりますが、大学には教育があります。ものを開発するのではなくて、基礎からの研究ですね。
坂本:企業の研究には、社会に貢献するということも企業理念としてあるとは思いますが、どうしても利益が重要視されます。大学は、利益を優先せずに社会にどれだけ貢献できるかという視点で取り組むことができるのが、大きな違いかなと思っています。
伊藤:管理栄養士の国家試験だけを考えると年間9,000人ぐらい、毎年、8,000〜9,000人が国家試験に合格します。その中で、この学科の設立時の理念である「リーダーとなれる管理栄養士」を養成していく。研究もできるリーダーになり得る管理栄養士を育てることが責務だと思っています。
永井:先生方のお話をお聞きして、管理栄養士がめざすのは、食を通じて人々を幸せにすることでは、と思えました。朝ドラの「おむすび」でも、患者さんが食べて幸せそうな顔をする時に、主人公も喜び、やり甲斐を感じていました。食と栄養の専門的な知識を学び、それを力として人を幸せにし、社会を豊かにしていく仕事が管理栄養士なんですね。そんな未来像や志を原動力にして、ぜひ本学で学び、羽ばたいていただきたいなと思います。

座談会が行われた実習食堂のあるS棟