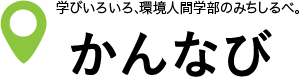地域への活動を通して学び、人口縮小時代における理想の都市像を探求(杉山武志ゼミ)【兵庫県立明石北高校出身】

「地域」って学問になるの?環境人間学部なら学べる!
文武両道を学校目標にかかげ、生徒の意識も高く勉強熱心な高校でした。私は参考書を読み込むというより、国語や世界史の授業で先生の話を聞いて知識を深めることが好きでした。部活はソフトテニス部に所属。部員とは今でも続く交友関係を築くことができました。
環境人間学部を知ったのは、高校3年生の春、担任の先生との面談がはじめでした。文系の学部といえば文学部や法学部などですが、どの学部もしっくりすることができず悩んでいた私に先生から「社会が得意だから、その中に好きなことがあるのでは?」と尋ねられ、自分の中にある興味の先を考えました。
幼い頃から、両親がよくいろいろな地域に連れて行ってくれました。行く先々のまちや自然の中で遊んだ経験により、その地域に関心を持ち、愛着を抱くようになりました。「地元や地域への愛着って何?学問になるのか?」担任の先生に相談したところ、「環境人間学部の社会デザイン系なら、社会や地域について幅広く学べるんじゃないか」とアドバイスをいただきました。すぐに、自分でも環境人間学部のホームページを調べ「ここなら地域について学べる!」。求めていた学部をみつけることができて、心が楽になったのを覚えています。
無事に大学合格を決め、卒業旅行としてテニス部の部員たちと自転車で淡路島を巡る日帰り旅行へ。坂道、下り坂と過酷な道のりでしたが、エンジンのない自分の足でまちを巡ったことで、地域の魅力をより肌で感じることができ「地域が好きだ」という気持ちを再確認できました。

環境人間学部の幅広い学びは、どれも面白い。「地域」について学びを深めるため、社会デザイン系へ
1年次、興味の幅が広い私にとって環境人間学部のすべての授業が楽しみでした。当時、コロナ禍でほとんどの授業がウェブで行われたこともあり、シラバスを見て面白そうだと思った授業を気軽に履修することができました。
「国文学(小説)」では、「雨月物語」について学びました、15回ある授業すべてを使って一つの作品について深堀りして学ぶことが、とても新鮮で印象に残っています。先生のこの作品にかける熱量も感じました。
他の授業でも、先生自身が研究されている専門分野の一部をみせていただいているような楽しさがあり、特に「地域」の単語がキーワードの講義はとても興味深く受講しました。
また、地域に出て何か活動したいという思いから、兵庫県立大学の副専攻「地域創生人材教育プログラム(RREP)」を受講。最初のフィールドワークで、私たちの班は神戸市垂水区塩屋町を訪れ、地元の方々にインタビューをさせていただきました。塩屋町では、明治、大正時代の外国人居住地「旧グッゲンハイム邸」を中心にさまざまなイベントが住民発信で開催されていて、地域の力を感じることができました。
2年次からは、もっと「地域」について学びたいと、社会デザイン系に進みました。
副専攻「地域創生人材教育プログラム(RREP)」で、子育て世代のためのイベントを開催
2年次、RREPで三田市をフィールドに三田市が抱える課題を捉え、課題解決のためのイベントを実施しました。
三田市を実際に歩いてみると、昔、開発されたニュータウンのまちなみに子どもの姿はなく、少子高齢化が進んでいることを実感しました。また、子育て世代の方へのインタビューで「子育ての悩みを共有できる場所が欲しい」という声を聞きました。
そこで、私たちは兵庫県立「人と自然の博物館」で、子育て世代の親子が交流を広げるきっかけになればと、親子対象のイベントを企画。コミュニティスペースに置く椅子に子どもたちが自由に色付する『ひとはくアーテ椅子ト』を実施しました。

さらに、参加者からの「他のイベントもして欲しい」との要望を受け、2週間後に『大きなツリーで!ひとあしはやいくリスマス』を開催。駐車場に大きなクリスマスツリーをチョークで描き、その上から子供たちにデコレーションをしてもらいました。クイズに答えるたびに使えるチョークが増えるルールを設定し、子どもたちのワクワク感を高める工夫も行いました。
短期間に2つのイベントを企画して実施するのは大変でしたが、他学部の人たちと同じ目標を持ち、協力して行う作業は楽しく充実していました。私は広報を担当し、ダジャレの本を読みキャッチーなイベント名をつけたり、子育て世代の親子が目につくチラシの掲示方法や配布場所を考えたりしました。結果、50組100名以上の親子に参加していただくことができ、達成感を味わうことができました。
イベント後には、まちづくり協議会の方や三田市の方の前で発表し、今後、三田市においてどのような政策が必要かを提案する機会もあり、貴重な経験となりました。


「縮小都市論」を軸に論文を書きたい。地域コミュニティや都市・地域政策が専門の杉山ゼミへ
2年次、「環境人間学演習Ⅰ」の授業で、杉山武志先生の指導のもと、西脇市へフィールドワークに訪れました。主に西脇市の特産品について触れ、播州織の工場の人へのインタビューをはじめ、いちごやお酒の特産品をどのように広めているのかを市職員の方にお聞きしました。授業では、インタビューで分かった西脇市の取り組みをまとめ、今後、必要とされる活動について考えました。
杉山先生の授業でのフィールドワークはRREPの活動と通じるものがあり、杉山先生のもとでなら、さらに地域について学び、私がしたいと思っている研究ができるのではとゼミ訪問に伺いました。
ゼミ訪問で杉山先生に、2年次に受講した太田尚孝先生の「まちづくり論」の課題レポート作成のために『縮小ニッポンの衝撃』(NHKスペシャル取材班著)を読み、「人口減少と地域の活力の関係性」について興味を持ち、研究してみたいとお話ししました。
すると、杉山先生から「縮小都市論」という学問があることを教えていただき、さらに『縮小都市の挑戦』(矢作弘著)を読むように勧められました。それは、人口減少に対して、新しい建物を建てることで人を集めようとする動きがあるが、それでは地域の昔ながらのまちなみを失い、同時に住民の地域への愛着も失ってしまう。今、まちにある魅力的なものを活用することで地域の活力にならないかという内容の本でした。
まさに、私の考えていたことがまとめられていた驚きと、この本を軸に研究を進め、論文を書き上げたいと思い、杉山ゼミに入ることを決めました。
卒業研究「人口縮小時代の都市政策像とローカル経済の役割―コンパクトシティ政策と創造都市政策をこえてー」
杉山ゼミでは、2年次の春休みにゼミの先輩方の話や杉山先生の研究の方向性を聞き、ゼミの始まる3年次4月には、自分の研究テーマを決めてスタートします。私は2週間に5~6冊のペースで研究テーマに沿った本を読んではレポートにまとめ、先生から「方向性が合っているかどうか」「さらにこの本を読むように」などのアドバイスをいただきながら進め、3年次の夏には卒業論文の大筋を決めることができました。
そこからは、神戸市の「都市計画マスタープラン」や横浜市の「横浜市中期計画2022~2025」など10都市の政策文章をまとめ、コンパクトシティ政策や創造都市政策の実態を把握。その上で、「縮小都市論」の理想的なまちをRREPのフィールドワークで訪れた塩屋町と捉え、調査を始めました。
塩屋町は、阪神大震災の影響が少なかったこともあり、昔のまちなみが多く残っています。そのまちなみに誇りを持ち、守っていこうという気持ちが多くの活動を生み、まちに活力が溢れています。私は、その活動の中心的な人物にインタビューを実施。塩屋町の魅力をどのように発信し、広めているのかをお聞きしました。
塩屋町には、大手チェーン店がなく商店街の人たちと住民が顔なじみで、コミュニティが力強く残っていることが大きいと話されました。コミュニティの中でうまれる「こんなイベントがあれば面白いね」という声をもとに、住民がまちを歩き面白い風景を写真に撮りまとめた『塩屋百景』の出版や、住民たちが各々楽器を持ち込みオーケストラとしてまちを練り歩くイベントなどが開催されています。数多くのイベントを通して住民はその土地に愛着を強め、参加した別の地域の人たちも塩屋町に住みたいと思うといった仕組みが出来上がっています。
卒業論文では塩屋町の事例をもとに、多少の人口の増減に縛られず、まちにもともとある魅力的な文化や住民の力を結集させ、地域の活力を穏やかに維持していく必要性を唱えたいと思っています。


私の理想の都市像「神戸市」に就職 文化を守り、継承していきたい
授業や研究でいろいろな地域に触れさせていただく中で、地域において現状を把握し、イベントをしたり、住民の方と触れ合ったりできる公務員という仕事に魅力を感じ、3年次から、キャンパスで開講されている「公務員講座」を受講して公務員試験対策を始めました。
就職活動では、「一緒に働きたいと感じるか」を常に考えていました。神戸市役所の説明会に参加した際、職員の方の神戸市への愛や熱意を強く感じることができました。
私の卒業研究での調査においても、神戸市はもともとある港町の雰囲気を残して文化を進めていくことに重きを置いていて、私の理想とする都市像でもありました。面接では、神戸市のこうした取り組みの多くを紹介させていただき、私の研究の成果と熱量を感じてもらえたと思います。おかげで、神戸市への就職が決まり、就職後は、神戸市の良さを発信できるような活動をしたいと楽しみにしています。
自分の興味をみつけるヒントを見逃さないで
幅広く学べる環境人間学部だからこそ、一つ一つの学びを大切にして、自分が少しでも興味のあることが見つかれば、一歩踏み出してほしいです。
私も「地域」という小さな興味から一歩踏み出すことで、RREPの活動、ゼミ研究と進めることができました。
進路選択に不安を抱えている方は少なくないと思います。いつもの授業を集中して聞いてみたり、自分の好きなことを紙に書いてみたりするなど、身近な範囲に自分の興味を知るヒントがあるかもしれませんよ。