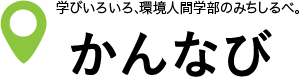【フィールドワーク】農村・ため池の課題解決に挑戦~受講学生が取り組んだこと、得たものとは?

環境人間学部に設置されているエコ・ヒューマン地域連携センターでは、地域連携活動を促す一環として、特別フィールドワーク「農村とため池が教室だ!ため池アクション!!」という授業を2023年度から実施しています。今回は、2023年度に参加した学生が、2024年度に参加した学生(1、2回生)に、活動内容や活動を通して感じたこと、考えたことについてインタビューをおこないました。
ため池アクションとは?
受講生が3つのチームに分かれ、地域住民や専門家、ファシリテーターと共に、農業・農村が抱える課題の解決を目指して活動を行う授業です。2024年度は、参加学生数は12名(1~2回生)、2024.5月から10月までの6か月間、3つのチーム(テーマ)に分かれて活動しました。活動場所は、加古川市や稲美町の農村です。
詳しくはコチラ
関係人口増加を目指し、地域の魅力を広めるべくイベントを実施
「ふる里づくりチーム」 (1回生3名)
本チームは、「次代に繋げる”ふる里”をつくろう!」をテーマに活動しました。「地域を次の世代につなげるにはどうしたらよいのか」という問いを掲げ、地蔵盆やカヌー大会などへの参加を通して地域住民との交流を深めつつ、地域の魅力を知る人を増やすためのウォーキングイベントを企画・運営しました。期間開催で自由に散策してもらいつつ、休日は地域住民と交流できる場を公民館に設け、フォトコンテストや笹舟流し、微生物観察会、さつまいもスティック作りなどを実施しました。

ため池周辺を散策
もっと関係性を深めるために。学生が地域に泊まれる仕組みを構築
拠点づくりチーム(1回生2名、2回生3名)
本チームは「ワーキングホリデー制度 in 広尾東を作ろう!」をテーマに活動しました。「関係人口」とは何なのか、どうなったら関係人口と言えるのかを紐解き、まずは自分たちが体現しよう!とアクションを起こしました。集落内で活動するにあたって、学生が泊まれる拠点が欲しい!という発想から、公民館で宿泊できる仕組みづくりをおこないました。地域住民が大切に守ってきた公民館を利用するにあたって、公民館の歴史を学んだり、利用するためのルールブックを作成したり、地域に来た人が思い出を記録する「思い出ノート」も作成しました。

地域イベント終了時の集合写真
地元の方への調査をベースに、みらいを予測して水路プランを提案
水路プラン作成チーム(1回生3名、3回生1名)
本チームは「みらいの水路プランを提案しよう!」をテーマに活動を行いました。水路やため池は、地域住民が管理しており、その実態を知るために、地域住民にヒアリングを重ね、複雑に絡み合う問題の現状把握に挑戦しました(老朽化する水路やため池の堤体、減少する農業用水の利用者(農業者)、ゆえに増えるため池の管理者負担、決壊時に問われる管理者責任、ため池の上流部の開発によって増えるため池への雨水の流入量など)。そして、今後も地域住民が管理していくプラン、管理していかないプランを整理したうえで、それぞれの課題を整理しました。

若手農家へのヒアリングの様子
昨年度学生による、今年度参加学生へのインタビュー
昨年度、このプログラムに参加したKaさん(環境デザイン系)とYa(社会デザイン系)さんが、今年度参加した4人の学生にインタビューを行いました。

KaさんとYaさん
学生Ka:どこで、どんな活動をしていましたか?
学生Y:「ふる里づくりチーム」は、加古川市の北西部にある志方西地区で活動しました。「志方西を盛り上げていこう」というテーマで、前年に先輩方が関わっていたウォーキングプロジェクトを発展させる活動をしました。平日のズームミーティングと土日の地域訪問をあわせて、月3、4回活動した月もありました。
学生I、M:「拠点づくりチーム」の活動場所は加古川市北部の広尾東という農村でした。行ったことは月に1回くらい村に訪れて、歩いて、様子をいろいろ見てみる!あと、夏祭りに参加して手伝いしたり、農作業したり、公民館にみんなで泊まったりしました。
学生K:「水路プラン作成チーム」は稲美町の下草谷地区という地域で活動しました。主にやったことは、現場見学と地域の方からお話を聞くこと。ため池の現状と管理下で抱える問題を知って将来的にため池をどうするのか考えました。フィールドワークに行ったのは大体月1回ぐらい。それ以外にzoomオンラインでミーティング 月1回ぐらいして、最終発表の前の9、10月は合わせて10回ぐらいはしたと思います。


学生Ya:このプロジェクトに参加したきっかけを教えてください。
学生Y:前期に環境人間学部であった授業で柴崎先生が、ためアクションの話をしてくださり、興味があったから行ってみようかなって。
学生K:一緒です。それと、お母さんが仕事でため池に関わっていたことがありなんとなくため池っていうワードに親しみがあったこともきっかけの一つです。
学生M:私も授業で聞いて、農業体験ができると書いてあったので。
学生Ka:活動の中で印象に残っている出来事はありますか?
学生Y:「ふる里づくりチーム」ではウォーキングプロジェクトの中で笹船流しというイベントを企画しました。そのイベントの予行で、 地域の方と一緒に実際に笹船を流してみました。それが童心に帰れたようで、楽しかったことを覚えています。
学生I:私は、活動の一環で参加させていただいた夏祭りが1番印象に残っています。チケット販売したり、焼きそばとかを売ったり、盆踊りをしたり色々食べさせてもらったり…。その日にみんなで公民館に泊まったことも楽しかったです。

夏祭りの様子
学生M:活動しながら「地域に受け入れられているのか」という不安がどこかにずっとあったのですが、最後のフルドワークの時に、地域の代表の方が「地域の人と学生がお互い気を使わずに接せれる関係でありたい」と言ってくれたことが印象に残りました。
学生K:「水路プラン作成チーム」の1回目のフィールドワークが雨の日で、水路に木くずが詰まっていて、少し決壊しいている状況を見ました。そして、その場で地域の方が草を手で取って、直している姿を見て、水路が老朽していることを実感しました。また、ため池に関わっている人、地域住民など、いろんな立場の人から話を聞けたことが印象的でした。

老朽化している水路の様子
学生Ya:参加する前と後で、地域に対する印象で変わったことはありますか?
学生Y:はじめに志方西と聞いた時は全然知らない場所だったので、田舎なんだろうな…地方での人口減少も問題になってるんだろうな…とすごいふわっとした感覚でした。 それが地域の人たちの声を実際に聞くとそんなふわっとした意識ではなくて、毎回どれくらい人数が減っていっているかとか、そのために何をしたらいいかとかを真剣に考えていることが伝わってきて、現実味が自分の中で増しました。
学生I :農村と言ったら、活動的ではないイメージが大きかったのですが 、みなさん元気で、毎週交流会などの活動をしていると聞いて驚きました。
学生M :地域に入っていく時にもっとよそ者感があるのかなと心配していましたが、実際行ってみたら、地域の人が温かく受け入れてくださったのが印象的でした。
学生K:自分たちがすべて主体になって活動していくのかという不安と、自分たちが半年入ったら何か問題を変えることはできるのではないかという期待がありました。けど、 実際入ってみたら、予想以上に地域が抱える問題が複雑だった…。難しいけど、地域の方やコーディネータの方が助けてくれたので、難しい問題にも手を付けていけました。また、地域の問題は半年で何かが大きく変わるわけでもなく、ちょっとずつしか進まないということを実感しました。


学生Ka:活動してみて自分の中でなんか変わったことがあれば教えてください。
学生Y :自分の中でその活動を起こすことに関して、簡単に捉えていた部分があって、半年あれば何か大きなことができるのではないかと軽く捉えていて、現実を見れていませんでした。また、人が動くことについてもあまり分かっていませんでした。自分たちの案がコーディネーターなどの身近な人を通り、地域の人たちに提案して、そこでいい反応が返ってきて初めて、やっと動き始められるんですね。そこで、人を経由して意見を伝えていくということがすごい大変でした。でも地域の人たちが優しく受け入れてくださり安心して活動を進められました。
学生I :友達が増えたことが自分の中で変わったことです。学年違う人とも仲良くなれました。
学生M:私は新しく何かを始めることに苦手意識があったんですけど、今回の活動を通して、 ちょっと楽しいなって思えるようになりました。 例えば、私が何か始めてもどうせ変わらんやんとか思ってしまうんですよ。 でも、ちっちゃいことやったら、ちょっとずつ変えることができるのかなと思えるようになりました。
学生K:自分の地元でもない、全然関係ない地域の人との繋がりができたこと が新鮮でした。LINEで雑談するくらいの繋がりができました。あとは、地域に入ること、人と人との繋がりに入ることをめんどくさいことだと思っていました。でも、活動を通して地域に入ることのハードルが下がりました。
学生Ya:コース選択とか就職とか、自分のキャリアを選択するにあたって影響を受けた部分はありますか?
学生Y:どのキャリアに行っても、活動を通して会ったことのない人と話した経験は活かせると思います。特に、行政の方々と関われたことがよかったかなと思います。行政の方々が、どういう視点で地域を捉えているのか、垣間見れた気がします。
学生K:両親の関係もあり、公務員は大変な職業だと思っていましたが、その苦手意識は薄れました。自分の将来に公務員という選択肢も入ってきたかなと思います。 それは、地域にも入ってみたら難しい部分もあるけど案外いけると思えたからです。公務員になったり、地域に入っていくのも全く無理な話でもないなってことに気づきました。
学生Ka:これから、各地域とどのように関わっていきたいですか。
学生Y: 今よりも、さらに地域の人たち個人個人と関わって行きたいです。
学生I:夏祭りやコスモス祭りの行事に参加して、お手伝いしていきたいです。
学生M:用がなくても、ふらっと立ち寄れるような関係でありたいので、たまに顔を出して、地域の人と会話などを楽しみたいですね。
学生K:活動を通してまとめた、ため池に関する話をウォークラリーのイベントで住民の方に発表して、その反応を見て、これから自分にできることを考えていきたいと思います 。
学生Ya:どんな人にため池アクションをお勧めしたいですか。
学生Y:人と人との間に入って何かするのが好きな人。それが得意ではないけれども、将来自分の地域のために何かしたいなと考えている人だと思います。
学生I:私はグループワークが得意であったり、グループワークの力をつけたい人におすすめです。
学生M:新しい人間関係を作りたい人におすすめです。
学生K :座学で得られない専門的な学びも得られるので新しいことを学びたい人、挑戦したい人にいいと思います。

おわりに
学生Ya:2023年度に活動に参加し、2024年度はサポーターとして活動を共にしてきました。今回もまたたくさん悩み、たくさん笑った半年になりました。生まれ育った場所とは違う地域で関係を築き、課題を見つめ、何かを提案するという貴重な経験は「ため池アクション!」の強みだと思います。この活動を通して、私たちは新たな繋がりと、新たな考え方や価値観を得ることができました。地域の課題は少しずつ形を変えながらも完全に尽きることはありません。私たちに大きな気づきと心のよりどころを与えてくださった各地域に感謝しながら、まだまだ課題と向き合っていきたいと思います!次回のアクションやその他のイベントであなたの参加を待っています。
担当教員(柴崎浩平):ため池アクションの狙いの一つは、「期間終了後も地域に訪れたいな」という思いを学生が持ち、継続的に地域に関わる関係性を構築することにあります。実際、受講した学生の多くは、様々な地域活動に参加したり、なかには学生団体を立ち上げた学生もいます。このような関係性を構築できたのも、地域のことを学びたいという学生の積極的な姿勢、それを受け入れてくださる地域住民がいたからです。農山村が抱える課題は多くあり、一朝一夕に解決できないですが、「学生と構築できた関係性は宝だ」と、地域の方がおっしゃっていたことが印象的でした。今後も本授業などを通し、「宝」になるような関係性を築く取り組みをおこなっていけたらと思います。