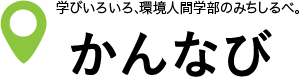人の行動を誘発する空間を研究~街区公園の魅力を客観的視点から評価(安枝英俊ゼミ)【兵庫県立明石高校出身】

家族の幸せの場所を作る建築士に憧れ。大学で「建築」を学びたい
高校生活は、入学式の代表挨拶から始まりました。もともと人前で話すことが苦手で緊張しました。入学後、苦手を克服したい思いから、放送部に入部。イベントやお昼の放送などに取り組みました。
進路については、模試を受ける度に志望校を書くので自ずと意識していました。私の希望は、兵庫県の実家から通える国公立大学で「建築」を学べることでした。
幼い頃、住宅チラシの間取りを見て生活を想像することが好きで、テレビ番組『大改造‼劇的ビフォーアフター』で建築士という仕事を知り、家族の幸せな暮らしを詰め込んだ場所を作りだせる素敵な仕事だと憧れを持つようになりました。
私の志望条件を満たしてくれる大学が少なく、不安になった時期もありました。そんな時、担任の先生をはじめ高校の先生方が、親身になって相談に乗ってくださり、いろいろな大学を探してくださいました。おかげで、選択肢の幅を広げて受験に臨むことができました。
環境人間学部は、建築はもちろん、建築以外の多様な分野を横断的に学べるところに魅力を感じ受験しましたが、入学時は、まだ、環境人間学部で建築を学ぶ本当の意義を分かっていなかったと思います。
1年次、広い分野を学ぶことで視野を広げ、 「まちづくり」の面白さを知る
入学して履修登録する際、建築に関わる授業だけでなく、シラバスを読んで自分の興味のありそうな授業を積極的に受講しました。1年次の必修科目「基礎ゼミナール」で社会デザイン系の太田尚孝先生のクラスで「まちづくり」の楽しさに触れるなど、いろいろな分野の先生の授業を受けて視野を広げることができました。
2年次で環境デザイン系に進んだ後も、太田先生の授業「まちづくり論」「都市計画論」を受講。この法律があるから土地をセットバックして道路が作られているなど、都市空間が形成される過程を都市計画的視点で学べ、とても面白かったです。今まで建築そのものという「点」に興味があった私が、建築を含むもっと広い「面=まち」に興味をもったきっかけになりました。
副専攻「地域創生リーダー教育プログラム」で地域の課題に取り組むプロジェクトを企画、実践
地域コミュニティに関わるいい機会になるのではと、全学の副専攻「地域創生リーダー教育プログラム(RREP)」を履修。1年次に受けたRREPの説明会で、公務員に技術系の仕事があることを初めて知り、建築の立場から地域に携われる仕事に興味を持ちました。
1年次の後期、淡路島の地域課題「竹林の担い手不足」を解決するためのプロジェクト『竹取の翁になろう!』を考案。淡路島移住者に得点を与える代わりに、竹林の保全を担ってもらうというものでした。
2年次では、三田市について調べ、「少子高齢化」と「若者の都市への流出」という二つの地域課題に着目し、『だらだらできる空間を作ろう!』という企画をたて、実践しました。「だらだらできる空間」を利用することで、地域への愛着が増すのではと考えたのです。コロナ禍で制約が多い時期だったのですが、三田市立図書館のご協力いただき、図書館の一室の照明を落とし、ハンモックやテントを置いて、普段とは違う空間を作り出しました。いつもは学習室として図書館を利用している中高生が来てくれてとても嬉しかったです。
RREPでは、他学部の人たちと班を組み、意見を出しあえるのが魅力の一つ。学んでいるものが違うと考え方も違い、アイデアがいろんな視点から出され刺激を受けました。

安枝先生の「建築計画論」の「60分設計」で 人の行動を促す設計にチャレンジ
安枝先生の「建築計画論」の授業では、建築物がどのような意図をもって作られ、空間を生み、利用者の行動へとつなげているのか、その仕組みを学びました。60分の制限時間内に授業で習った仕掛け、工夫を盛り込んで自由設計をする「60分設計」で、シェアハウスの設計をしました。私は、個々の居室の中央にシャワー、トイレのユニットを配置し、一人で過ごすプライベートゾーンと人と交流が持てるパブリックゾーンとに空間を分けて使えるように設計。出来上がった設計を、意図を説明しながらプレゼンしました。他の人のプレゼンを聞くことで、同じ意図であっても、違うプランを見て、設計の意図を知ることはとても勉強になると安枝先生に教えていただきました。
この授業を通して、建築そのもののデザイン性を追求するよりも、建築の意図、工夫によって使う人の行動をどう促すのかというような建築計画についてもっと学びたいと思うようになり、3年次からは安枝ゼミで研究することに決めました。
幼い頃から大好きだった「公園」 。その魅力を客観的視点から評価する
私の卒業研究のテーマを決めたのは、3年生の夏ごろでした。太田先生の授業「都市空間分析演習」で、地理情報システム「GIS」を使って、高砂市の都市公園の立地の特徴を分析し、国土交通省から出されている「街中の公共空間の居心地の良さの指標」を基に公園を点数化してまとめた課題レポートを安枝先生が見られて、卒業研究のテーマとして「公園を研究してみては?」とご提案いただいたのがきっかけでした。
小さい頃から「公園」という存在に癒されてきました。祖父とよく散歩した楽しい思い出が今でも残っています。この感情はどこから来るのか、公園の魅力を客観的な視点から評価する研究をすることにしました。
まずは、客観的視点を見つけ出すだめ、安枝先生とのやりとりを繰り返しました。結果、姫路市第一地区および城北校区内における街区公園について、①公園内部にある植栽、②街路などの外部空間との関係、この2つの視点から利用しやすさを分析することに。例えば、「樹冠の大きな木が利用者の居場所になる」ことに重きを置いて、樹冠の大きな木の配置、樹冠の下には利用者が滞留できるしつらえになっているかなどを中心に、公園の空間的特徴を航空写真やストリートビュー、樹木データを使って整理し、対象公園を絞っていきます。次に、人流データを重ねてみて、多くの人が滞留している公園をピックアップ。現地に赴き、実際の滞留の様子を調査、分析することで、魅力的な公園を客観的視点から評価したいと思っています。



建築の知識を活かし、地域に貢献したい。地方公務員の建築職を目指す。
入学前から建築士に憧れて、将来は、設計事務所かゼネコンで働きたいと考えていました。でも、入学して、設計の授業が進むにつれ、自分の頭の中に浮かぶアイデアを図面におとすことが難しく、納得いく作品を作り上げることができませんでした。就職を考えた時、幼い頃夢見たような設計して、空間を作ってお金を稼ぐことは難しいと思うようになりました。代わりに、大学の学びや研究を通して興味をもった「まちづくり」や「地域コミュニティ」に建築の知識を活かせる地方公務員の建築職を目指すようになりました。これは、環境人間学部で幅広い分野を学べたからこそ、導きだせた道だと思っています。
3年次の春からキャンパス内で開講されている公務員講座を受講。3年の夏には京都市役所、相生市役所でインターンに参加しました。京都市役所では、建設中だった福祉施設の現場を見学させていただきました。設計の意図を聞きながら建物内をめぐることができ、とても貴重な経験となりました。相生市役所では農林水産課、下水道課、都市整備課でお世話になりました。使われなくなった獣害対策の檻の撤去やダムの点検、工事中の階段の確認、建設中の道路など多くの現場に連れて行っていただき、市役所職員の様々な仕事に触れることができました。
ありがたいことに明石市役所の建築職として採用が決まり、市民の人々にとって居心地のいい場所、心がやすまるような空間を作ることに少しでも貢献できればと思っています。そのためにも、1級建築士の資格取得も目指しています。
後輩のみなさんには、やりたいことがあれば、勉強であれ、趣味であれ、遊びであれ、時間のあるうちにやっておくことが大切だと思います。私は目の前のことに必死に取り組むことで、充実した4年間を過ごすことができました。自分のペースで大学生活を楽しでほしいと思います。