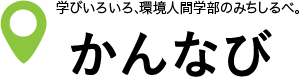授業での学びを活かして不動産業界へのパスポート「宅地建物取引士(国家資格)」に合格!体験談を合格者に聞きました。

不動産業界?宅地建物取引士??
皆さんの生活と深く関係する土地や建物などの不動産。
大学生で一人暮らしをしている人は部屋探しでまちの不動産会社にお世話になった経験もあると思います。不動産業界は、マンションや戸建て住宅の賃貸や売買だけではなく、施設の維持管理や、空き家・空き地問題の解決にも関わってきます。さらに都市開発など、皆さんが休日に買い物や遊びに行くような場所をつくるのも不動産業界の仕事です。
この中で、不動産取引の専門家が宅地建物取引士(宅建士と省略されることもあります)です。宅地建物取引士は国家資格として、別名「不動産業界へのパスポート」と呼ばれます。この資格を持つと企業によっては資格手当が支給され、扱える仕事の幅も広がります。そのため、不動産業界以外にも建築や金融など、様々な業界を目指す学生が学生の間に資格を取得しようとしています。
試験は「宅建業法」「権利関係(民法など」「法令上の制限」「税・その他」の4科目、50問。日本国内に居住する人であれば、年齢や学歴等に関係なく、誰でも受験できるのが大きな特徴です。令和6年度は10月20日(日)に全国260会場にて試験が開催されました。受験者数はなんと241,436人!合格率18.6%という狭き門に合格した環境人間学部の学生に話を聞いてみました!
Aさん(4年生)、Bさん(3年生)にはインタビューにご協力いただきました。また、2年生の合格者4名についてはアンケートに回答してもらいました。

Aさん

Bさん
宅建士資格を受験しようと思ったきっかけは?
【Aさん】
不動産業界に就職活動をおこなうためのアドバンテージとしたかったからです。ある会社のインターンシップで「不動産業界では、宅建は運転免許証みたいなものです。今では持っていて当たり前の時代になっています。」と話を聞き、宅建受験を意識するようになりました。それに、働き始めてから勉強を両立するのは大変そうだと思ったこともあり、今のタイミングで受験することを決意しました。
【Bさん】
将来不動産関係の仕事に就きたいと考えていたため、学生のうちに取得しておきたいと考えていました。その中で「宅建受験応募締め切り2日前」という広告を偶然見て、受験を決めました。また現在都市計画研究室に所属しているため、資格取得を通して都市計画・不動産の知見を深めようと考えたこともキッカケの1つです。
【アンケート結果】
・ 先生が「まちづくり論」の授業時に宅建をとることを勧めていたり、日建学院の方の話をきいたりして受けようと思った。
・ 1年の終わり頃から将来都市計画に携わる職業に就きたいと考えており、2年前期の「まちづくり論」の講義を受けていた。その講義内で市内のスクールの方がお話をしに来て下さったり、太田先生も宅建は取っておいた方がいいとおっしゃっていたりして、いつか取ろうから学生のうちに取っておこうに変わった。
・ 大学生のうちに何か資格を取りたいと思っており、太田先生の「まちづくり論」の講義を受けて、宅建という資格に興味を持ったから。
・ 授業で宅建をとったらいいよと先生がおっしゃっており、自分も大学生活で時間がある今、なにか頑張りたいと思ったタイミングだったから。

いつ頃から勉強を始めた?
【Aさん】
本試験の半年前です。私は日建学院に通っていたのですが、日建学院のカリキュラムが4月からのスタートだったからです。何かに合格するために点数を意識しながら勉強をすることは大学受験ぶりだったので、はじめのうちは勉強を習慣化することから苦労していました。インプットにもアウトプットにも十分に時間を割くことができたので、半年間の勉強期間は妥当でした。逆にスタートが早すぎると、10月まで宅建を勉強する体力とモチベーションを保つことが難しいと思うので、半年くらいがちょうどいいと思います。
【Bさん】
学校がある期間は研究室活動や部活動で忙しかったので夏休み(8月上旬)から始めました。試験までの期間が短かったため8月は1日2,3時間、9、10月には1日6,7時間といった感じで集中的に取り組むことを意識しました。合格する事は出来たものの、スケジュール的にはかなりタイトになってしまったため、試験の半年前くらいから勉強を始めるのが一番理想的だったと振り返ってみて思います。
【アンケート結果】
・ 5月頃です。
・ 2年の5月(試験本番の5~6ヶ月前)。
・ 5月の初旬。
・ 5月上旬。
資格取得にむけてスクールに通う?それとも独学で?(その理由も教えてください)
【Aさん】
スクール派です。初めて挑戦する資格で、何をどのように勉強したらいいのか自分では分からないため、勉強方法のマネジメントを全てスクールに任せることができるからです。インプットの時期とアウトプットの時期が切り分けられており、効率よくかつ効果的に学習できたと思います。毎回ウェブで提出する宿題があり、一定の点数を取らないと回答が表示されないというシステムになっているので、頑張らざるを得ない状況であることも、私の性格的に合っていました。また、周りの人も頑張っていることが目に見える環境であるため、モチベーションを維持することもできます。実は去年に通信講座で宅建を取ろうとしたのですが、親にお金も払ってもらったにも関わらず途中でやめってしまったので、「今年こそはスクールに通って、一発合格だ!」と気を引き締めて頑張りました。

【Bさん】
独学派です。今までの経験上誰かに強要されず、自分の好きなタイミングで好きな内容を勉強する方が自分には合っていたので、比較的自由度の高い独学という方法を選択しました。加えて大学受験も過去の資格試験も独学で乗り越えてきたので、宅建士に関しても独学で合格したいという想いがあったことも理由の一つです。
独学のメリットは、プレッシャーを感じなくて済むところ。スクールだと「合格しないと」という使命感が出てくると考えました。また、スクールと比較すると費用がかなり抑えられます。スクールは、過去問やテキスト・講義などが充実している分、費用も3万~30万程度とやや高額です。一方で独学ではテキストと過去問さえあれば勉強を始められる為、数千円から、高くても数万円程度しかかかりません。私の場合、実際にかかった費用(受験料を除く)は5000円程度でした。
独学により、のびのびと勉強できたと感じる反面、周りに宅建士受験をする仲間がおらず、孤独感を感じることがたびたびあったので、そういう点ではスクールのように、同じ目標を持つ仲間がいる環境で勉強できるのは羨ましかったです。
【アンケート結果】
・ 独学で勉強しました。スクールはお金がかかるという理由で、今年落ちたら来年はスクールに通おうと思っていました。
・ スクール派(日建学院)。元々、都市計画に興味を持ち始めた時に参考書を買っていたが、ほとんど開いたことがなかったので、ある程度厳しい環境で、同じ目標に向かって頑張っている人の顔がはっきりと見られる方が、モチベーションになったり焦ったりするので頑張れた。
・ 独学派(ユーキャン)。自分に合った勉強方法を見つけることができるから。
・ スクール派。大学生にはかなり難しい知識を覚えるため、独学では難しいと思う。スクールで計画的にみんなと勉強する方がモチベ-ションもあまり落ちないと思う。
大学の講義は宅建士合格に役に立った?(役に立ったのであれば科目名も教えてください)
【Aさん】
役に立ちました。「まちづくり論」、「都市計画」、「建築法規」の3つです。その授業の中では完全に理解しきれていなくても、宅建の勉強をはじめたときに「何となくでもイメージができる」「一度勉強をしたので用語に親しみがある」という状態であったことが、とても助かりました(法令上の制限の科目。宅建業法の次に、得点源にしなければならない科目です)。専門用語を目にしたときに、それだけで拒絶反応を起こしてしまいそうになるのですが、専門用語が多い法令上の制限を得意科目にできたことは、大学での授業で一度勉強したおかげだと思っています。その他にも、「現代家族と法」は、権利関係の科目で相続の問題がほぼ毎年出るのですが、「現代家族と法」の授業の中で相続について勉強したことや家系図を書く癖がついたことが宅建にも役立ちました。
【Bさん】
「都市計画」の講義が役に立ったと感じました。用途地域や区域区分などの考え方をある程度理解していたので、「法令上の制限」の分野の勉強は取っ掛かりやすかったです。それから「現代家族と法」も講義を通して相続や遺言など民法に関する知識を深めることが出来たため、宅建士試験の中でも特に「権利関係」の分野の勉強に役立ったと感じています。

【アンケート結果】
・ 「まちづくり論」
・ 「まちづくり論」
・ 「まちづくり論」
・ 「都市計画」
おすすめの勉強法は(おすすめ教材など)?
【Aさん】
はじめに権利関係の科目(民法)を学習し、苦手意識をなくすことです。権利関係は、出題数は50問中14問と多めですが、全てを理解することは難しいことから、メインの得点源ではないと言えます。ですが、全く得点できなければ合格が危ぶまれるため、全てを理解することを目的とするのではなく、時間がある内に頭を慣らすのがポイントだと思います。
直前の追い込み期間になると、得点源である宅建業法(50問中20問)と法令上の制限(50問中8問)を中心に復習することになります。その時期にあれこれ手を広げて復習をする余裕はないので、権利関係には早めに慣れておくことをオススメします。税・その他の科目と、5問免除科目は範囲も狭く、出題される箇所も限られているので、一通りインプットできたら、その後は息抜きがてら学習を進めてください。

【Bさん】
➀テキストを分野ごとに読む、 ②一問一答で確認。これを3周くらいして、最終的にはテキストのどこにどんな内容が書かれているか頭の中でイメージできる状態にします。最終的には過去問をひたすら解いて、確認します。また、電車で移動しているときなどにアプリを使って知識確認します。
テキストについては色んなものがありますが、知識量よりも、自分が見やすいデザイン、例えば、カラーリングとか文字が詰め詰め過ぎない等のテキストを選んだ方が疲れないと思います。私の場合は、LEC「宅建士トリセツ」のテキストと一問一答を使いました。
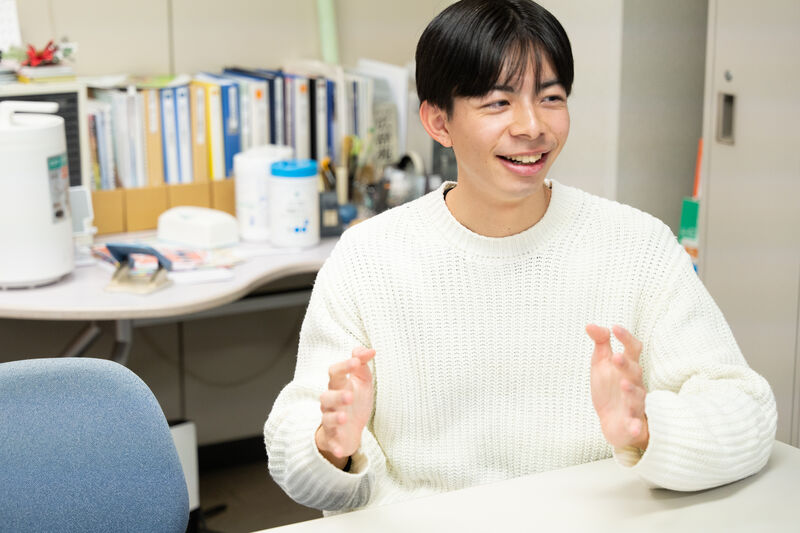
【アンケート結果】
・ 毎日図書館に通うこと、去年までの過去問を全てとく(早い段階で1年分といてみると難易度がわかる)。参考書では、宅建士合格のトリセツ、宅建士過去15年問題集です。
・ 模試などで繰り返し間違える問題や特に大切だと思うポイントなどをミニノートにまとめる。
・ スクールの教材(過去問、模試)。
・ ユーキャンの通信教育教材。
これから受験を考えている学生に一言!
【Aさん】
宅建は、勉強しないと合格できないけど、勉強すれば合格できる資格です。どういう意味かと言うと、不動産の仕事の経験がない大学生でも、きちんと勉強すれば合格できるということです。はじめは聞いたことがない言葉が出てきて混乱したり、難しい問題文に頭を悩ませることも多かったですが、インプットの時期を経て、アウトプットの練習を積むうちに、根拠をもって正誤を判断できる問題が増え、楽しくなりました。結果として「資格」という目に見える自分の武器となったため、合格した喜びだけでなく、資格を仕事で活かしながら今後も多くのことを得られそうです。チャレンジしやすい国家資格である宅地建物取引士、ぜひ皆さんも受験してみてください!

【Bさん】
Youtubeで「宅建士 勉強法」と調べると何十冊もの教材を使って合格している人がたくさん出てきますが、あまり色んな参考書に手を出さず、一冊を完璧にすれば十分合格は狙えると思います。個人的な経験則ですが、市販の本番前予想問題集は過去問と系統が異なる&難易度が高すぎて自信を無くすのでやらなくていいと思います。試験で気を付けるべきこととしては、民法を勉強しすぎないことです。「権利関係」の分野はテキストにはのっていないような細かい知識まで問われることもあります。しかし民法だけでも1000条以上あるように、全てを勉強するとなると膨大な時間がかかります。かつそこまで配点も高くはないので権利関係の分野については最低限を抑える程度で十分だと感じています。やっておいてよかったこととしては、FP2級を事前に取得したことです。FP2級は税金や相続など宅建士と試験分野と重なっている部分がいくつかあるので、その知識が宅建士の勉強でも活かされたと思います。プラスして、一度資格取得に挑戦しておくことで、ある程度のスケジュール感であったり、自己管理能力を磨くことが出来たと思います。

【アンケート結果】
・ 最初は分からなくても繰り返し参考書を読んだり問題をといたりすることで理解ができるようになるので途中で諦めずに頑張りましょう!早めに勉強を始めることをオススメします!
・ 色々と良い経験になり、やり切れたことが自信に繫がりました。
・ 今まで聞いたこともない単語ばかりで心が折れそうになりましたが、将来家を売買するときなど、生活する上で役に立つ資格だと思います!”
・ あまり興味がなくても、進めていけば面白いと思えるようになる気がします。

学生生活の中で資格取得に興味がある学生も多いと思います。
環境人間学部では幅広い学びが可能です。
多くの選択肢の一つとして宅建士もあるかもしれませんね。